作動原理
 暖房用としてのロケットストーブの関心の高さは、当ブログへの検索ワードでも判ります。
暖房用としてのロケットストーブの関心の高さは、当ブログへの検索ワードでも判ります。
日本の住居では設置が難しいと思われますが、興味あるストーブです。
所で、このストーブの特徴は、排気がきれいで、煙は引き出されるというより、押し出されるということらしい。
そのため、ストーブ本体から出た燃焼ガスは、そのまま、横方向に排出するという、通常のストーブでは考えられない構造になっています。
原理はどうなっているのでしょう?
国内サイトでは、納得できる解説を見つけられません。
また、L型の煙突をペール缶に埋め込んで、ロケットストーブを称しているものを多く見かけますが、これは、ロケットマスヒーターの、真の能力を出すものでもないと思います。
素人なりに、ロケットストーブについて、再度検証してみました。
(対象:200Lドラム缶を使用する、標準的なロケットストーブ)
燃焼ガスは、ヒートライザーと呼ばれる、いわば燃焼チャンバーで燃焼します。
ロケットストーブは、このヒートライザーが断熱材で覆われているのが大きな特徴です。
燃焼ガスは、ヒートライザーを昇り、アウターケースあるいは、ヒートエクスチェンジバレルと呼ばれる、200Lドラム缶内部で反転し下方向へ下ります。
インナーケースとアウターケースの上部、及びサイドのギャップはかなり重要で、約5cm程度。
ヒートライザーを昇った燃焼ガスは、ラジエターである、アウターケースで冷やされます。つまり、熱交換が行われます。
冷やされた燃焼ガスは、重くなり下降します。
当ブログの記事、「ロケットストーブ2(2009/10/13)」のイラストには、エギゾーストクーラー(排ガスクーラー)の記述があるが、この概念を象徴しています。
効率よく冷やすために、ギャップは広すぎてはいけません。また、クールダウンの影響をヒートライザーが受けないよう、断熱材(絶縁材)で覆われています。
そして、温度低下した燃焼ガスは、横煙道に入ります。
横煙道は太く大きな容量を持たせてあります。
燃焼ガスは、ここで膨張し、若干の温度低下を起こします。つまり、燃焼ガスを吸い出す機能を持つわけです。
横煙道は、冷えすぎると排ガス排出の妨げになりますし、ある程度の長さがは、外気の影響を受け難くしていると考えられます。
水平方向のまま排煙させてもいいし、垂直煙突を設ける場合もあります。
しかし、高い屋外煙突は、ロケットストーブにとって必ずしも良いことではないと考えられます。
もしも、屋外の垂直煙突が高く、横煙道の容量が極少量ならば、屋外煙突内部の冷えた燃焼ガスは、ストーブ内部に逆流する可能性があります。
しかし、最小の外部縦煙突と、粘土等で充分な断熱処理を施され、しかも、充分な長さを確保された横煙道は、外部縦煙突の影響を最小限に抑えると考えられます。
(実際、海外サイトでは、φ200㎜程度で、非常に長い横煙道を用いている)
断熱材でヒートライザーを覆い、高温状態の燃焼ガスの膨張を保ち、冷却によるガスの収縮を利用することにより、長い横煙道にもかかわらずスムースな排煙が可能となります。
また排ガスが、ほとんど臭わない、高効率、完全燃焼するというのも、このストーブの特徴です。
200Lドラムを使用する場合、燃焼スペースは、ほぼ決まっています。
そのためには、投入する薪の量と、吸込まれる空気の量が適正でなければなりません。
開発者のラリー・ウィニアルスキー博士は、燃焼ガスを高温に保つこと、コンスタントに空気を供給すること、ただし、過剰な空気や、2次空気は必要ない。多量の空気は燃焼ガスを冷やすからと述べています。
投入口は、およそφ150㎜。ヒートライザー長さ(高さ)は、約900~1000㎜です。
完全燃焼とはいえ、内部に溜まるであろう煤の掃除は、数年毎には必要ではないのでしょうか?
太い薪の投入が難しい(?)。つまり、始終薪を投入しなければならないのでは?
それが心配ではあります。
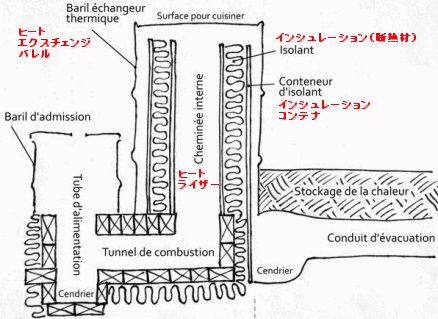 兎も角、かなり考えられたストーブだという事が判ります。
兎も角、かなり考えられたストーブだという事が判ります。
ノーテクと見過ごすべきではないことを知りました。
オリジナルの200Lドラムを使用したタイプが、最も効率がいいのだと思います。
また、日本式のソーダストストーブの燃焼方式と組み合わせたら、手間が省けて良いかもしれない・・とも。
(実物に接したことのない素人意見ですので、間違っている点はご指摘下さい)